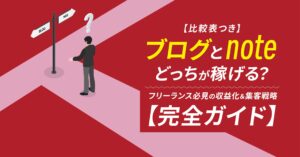近年、コンテンツマーケティングの重要性が増す中で、多くの企業が記事制作の体制について頭を悩ませています。
この記事を読んだあなたも、次のような疑問を持っているのではないでしょうか。
- 内製と外注、結局どちらが良いのか知りたい
- 自社に合った記事制作の方法がわからない
- リソースが限られている中でどう進めればいいのかわからない
結論から言うと、記事制作は内製化と外注を適切に組み合わせることで、コストを抑えつつ品質とスピードを両立させ、効果的なコンテンツマーケティングを実現できます。
今回は、記事制作の内製化と外注、それぞれのメリット・デメリットや、業種・目的別の最適な選択基準、そして内製化を成功させるためのステップと仕組みづくりについて詳しく解説します。
記事制作の担当者や経営者の方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
記事制作の内製化と外注、最適な選択を比較

記事制作の内製化と外注を検討する際には、以下のような観点から総合的に判断することが大切です。
- 内製化・外注のメリット・デメリットを比較
- 業種・目的別の最適な選択基準
- 社内リソースから見る判断ポイント
自社の業種特性や人的リソースを踏まえ、段階的な導入やハイブリッド型の活用も検討しながら、持続可能な記事制作体制を築いていきましょう。
内製化・外注のメリット・デメリットを比較
記事制作の内製化と外注には、それぞれメリット・デメリットがあります。適切な選択には、両者の特徴を理解することが不可欠です。
内製化の最大のメリットは、継続的なコスト削減効果と社内ノウハウの蓄積です。自社の専門知識を直接反映できるため、ブランドメッセージの一貫性を保ちやすく、中長期的なコンテンツ資産を構築できます。一方で、人材育成やツール導入に必要な初期投資は課題となる可能性があります。
一方、外注は専門ライターのスキルを活用し、短期間で多くの記事を制作できます。しかし、単発の依頼では単価が高くなる傾向があります。
また、品質管理には外部とのコミュニケーションコストがかかり、情報漏えいリスクも考慮しなければなりません。
| 比較項目 | 内製化 | 外注 |
|---|---|---|
| メリット | 継続的なコスト削減、ノウハウ蓄積 | 専門スキル活用、迅速な制作 |
| デメリット | 初期投資、人材育成 | 単価高、情報漏えいリスク |
技術解説記事など専門性の高いコンテンツは内製化が適しています。ディレクションを内製化し、ライティングのみを外注するハイブリッド手法を採用する企業も見られます。
AIを活用した内製化もおすすめ
近年AIの文章生成における進化はめざましく、人間が書いた文章と見分けがつかないほどです。AIによって高品質な文章の叩き台を作成できれば、外注可に伴うコストを大幅に削減できる可能性があります。
しかし「AIのプロンプトを作るのが大変」「AIの出力する記事の品質が悪い」とお悩みの方もいるでしょう。
AIライティングツールmagicssなら、キーワードを入力するだけで、ペルソナ分析から構成作成、記事制作まで一気通貫でSEO記事を制作できます。
これまで内製化にかかるコストが負担になっているのであれば、ぜひ一度magicssを活用してみてください。以下の公式サイトでは生成した記事サンプルが閲覧できるだけでなく、アカウント登録だけで1記事無料で記事を生成可能です。
あなたの執筆しているキーワードを入力して、magicssの記事のクオリティを実感してください。
業種・目的別の最適な選択基準
業種や目的によって、最適な記事制作方法は異なります。ECサイト運営の場合、商品知識を活かしたオリジナルコンテンツを作成できるため、ディレクションを社内で行い、ライターを外注するハイブリッド型が有効になるケースが多く見られます。
BtoB企業では専門性の高い技術情報が必要となるため、コア部分を内製化し、校正を外注する方法がよいでしょう。
ブランディングを重視する場合、社内のノウハウを反映できる内製化が有利です。検索エンジンからのトラフィック獲得が目的の場合は、SEO専門知識を持つ外注先との連携が効率的でしょう。
業種特性と予算を考慮した現実的な選択が、持続可能なコンテンツ戦略の鍵となります。
社内リソースから見る判断ポイント
記事制作の内製化を成功させるには、社内リソースの適切な把握が重要です。
編集、ライティング、SEOなど、各専門領域のスキル保有状況を部署横断的に把握します。
例えば、マーケティング部門にSEOの知識を持つ人材がいる場合、その活用方法を検討しましょう。
既存業務との兼務が可能かどうかは、1週間あたりの稼働可能時間をヒアリングし、数値化することが重要です。
| 判断基準 | 専任チーム事例 | 兼任体制事例 |
|---|---|---|
| 月間制作本数 | 20本以上 | 5本未満 |
| 必要スキル | SEO/編集/ライティング | 基礎ライティング |
段階的に移行する場合は、技術資料や製品マニュアルなど専門性の高いコンテンツから内製化を始めると効果的です。
3ヶ月ごとにKPIを設定し、リソース不足が判明した場合は外部ライターとの併用など、柔軟に対応しましょう。完璧を目指さず、改善を続けることが重要です。
KPIは重要業績評価指標のことで、目標達成度を数値で評価するための指標。売上や顧客数などが代表例。
記事制作の内製化で得られるメリットと課題

記事制作を内製化することで得られるメリットや直面しやすい課題は、以下のように整理できます。
- 【メリット①】独自の専門知識を活かして他社と差別化できる
- 【メリット②】社内ノウハウ蓄積による長期的価値がうまれる
- 【メリット③】意思決定が早くコミュニケーションが円滑になる
- 【課題①】人的コストと時間的制約
- 【課題②】専門スキル不足の対策
内製化を成功させるには、強みを活かしながらリソースを最適に配分する工夫が不可欠です。必要に応じて外部の専門家を活用し、継続的な改善を図りましょう。
【メリット①】独自の専門知識を活かして他社と差別化できる
自社の専門知識をコンテンツ制作に活かすことで、他社にはない独自性の高い記事を作成できます。
業界特有の課題解決ノウハウや現場の知見は、価値あるコンテンツを生み出す源泉です。自社の専門知識は、以下のように活用しましょう。
- 自社製品開発で得たデータの二次活用
- 顧客対応で蓄積したFAQの体系化
- 技術スタッフとの協業による専門解説
業界用語を適切に使い分け、顧客の潜在的な悩みを的確に表現できることが強みです。例えば、製造業向けコンテンツでは、専門用語を用いながら品質管理の手法を具体的に解説することで、読者の共感と信頼を得られます。
社内ナレッジを可視化することで、新人教育用マニュアルや営業資料の作成効率も向上します。あるIT企業では、外注ライターと連携する場合は、専門部分を社内が監修し、文章化を外注するハイブリッド方式が効果的です。
【メリット②】社内ノウハウ蓄積による長期的価値がうまれる
社内で記事制作を続ける最大のメリットは、組織の知的財産を体系化できることです。
制作プロセスを通じて、業界特有の専門用語の解釈や顧客の潜在的な悩みに対する対応策を見える化し、属人的な知識を組織資産に変えられます。
持続可能な成長を支える要素はおもに以下の通りです。
| 施策・取り組み | 効果・詳細 |
|---|---|
| 社員の異動や退職時の知識の断絶を防止 | 過去の制作データを検索可能な状態で保存 |
| 営業部門と連携したFAQデータベース構築 | 顧客の頻出質問への回答精度向上 |
| コンテンツ品質の基準値を明確化 | 新人教育時のトレーニング指標として活用 |
蓄積される編集ノウハウは、外注コストの最適化にもつながります。自社ライターが習得した記事構成のパターンや読者反応の分析データは、競合他社に真似できない独自の競争優位性となります。
特にトレンド変化が激しい業界では、迅速な情報更新が可能になる点が大きな強みだといえるでしょう。
【メリット③】意思決定が早くコミュニケーションが円滑になる
社内での記事制作は、意思決定のスピードと部門間連携の効率性を高めます。
外部委託の場合、修正依頼や方向性の変更には業者との調整が必要ですが、社内チームであれば迅速に対応できます。
例えば、公開直前の記事に営業部門から最新市場データの反映要請があった場合、すぐに編集チームと連携して修正できます。
進捗を見える化するための仕組みづくりには、定期的な進捗共有会議とクラウド型プロジェクト管理ツールの導入が効果的です。
- 週次ミーティングで全記事の制作ステータスを可視化
- タスク管理ツールで個別課題を早期発見・対応
- 社内チャットツールで即時フィードバックできる環境を構築
特に技術部門との連携が重要な専門記事では、エンジニアとの直接対話で正確な情報を迅速に反映できます。
ただし、円滑なコミュニケーションのためには、原稿依頼書やスタイルガイドなどの統一基準が必要です。
【課題①】人的コストと時間的制約
記事制作の内製化において、人的コストと時間的制約は見落としがちな課題です。社内人材が通常業務と並行してコンテンツ制作を行う場合、負荷分散の仕組みが必要です。
SEOライティングや編集スキルの習得には、最低3ヶ月〜6ヶ月かかります。特に検索エンジンのアルゴリズム更新に対応するために、継続的な学習時間が必要です。
段階的な移行プロセスとして、最初の3ヶ月は試験運用期間を設け、外注比率を50%から20%へ徐々に減らす方法が効果的です。
時間管理では、タスク可視化ツールと週次進捗確認会議で、計画通りに進行できる体制づくりが重要です。
【課題②】専門スキル不足の対策
専門スキル不足解消のためには、段階的な学習環境の整備と外部リソースの戦略的活用が効果的です。
まず、社内チームのスキルアップには、SEOやライティングの外部研修への参加が有効です。実務経験豊富な講師によるワークショップ型セミナーでは、体系的な知識と実践スキルを同時に習得できます。
また、社内勉強会の定期開催とオンライン学習プラットフォームを活用することで、常に最新トレンドを把握できます。
例えば、月1回の社内勉強会では、外部コンサルタントを招いたスキルチェックや記事の相互添削を実施すると効果的です。
さらに、外部リソースを戦略的に活用することで、自社の弱点を効率的に補強できます。
- 専門性の高い分野は外部ライターと協業(監修体制の構築)
- 業界専門誌やWebデザイン関連のオンラインコースを学習リソースとして活用
- コンサルタントによる四半期ごとのスキル診断と改善プランの作成
重要なのは「完璧な内製化」ではなく、自社の強みを活かせる分野にリソースを集中させることです。
編集力や自社製品知識を深めつつ、不足する専門領域はプロに任せる柔軟な姿勢が成功の鍵です。
記事制作を内製化する成功ステップと仕組み作り

記事制作を内製化して成功させるためには、以下のようなステップと仕組みづくりが不可欠です。
- 目的設定から始める段階的な導入プロセス
- 理想的なチーム構成と役割分担
- 品質を担保する制作マニュアルとチェックリスト
- 外注と併用するハイブリッドモデルの実例
段階的にスキルと体制を整えながら、必要に応じて外注を組み合わせることで、品質と効率を両立した持続可能なコンテンツ制作体制が構築できます。
目的設定から始める段階的な導入プロセス
記事制作の内製化を成功させるには、明確な目的設定と段階的な導入プロセスが必要です。「PV数10万突破」や「問い合わせ率3%向上」といった具体的な数値目標を設定しましょう。
目標が定まれば、3ヶ月・半年・1年単位のロードマップを設計できます。
フェーズ別の具体的な実施内容とハイブリッド移行のポイントは以下の通りです。
| 期間 | 実施内容 |
|---|---|
| 1-3ヶ月 | 自社の強み領域で週1本の記事制作 |
| 4-6ヶ月 | 専門性の高いコンテンツへ拡大 |
| 7-12ヶ月 | 外注比率を30%まで削減 |
また、完全内製化ではなくハイブリッド型の運用を成功させるには、以下のポイントが重要です。
- 外部ライターとの共同作業でノウハウを吸収
- 月次レビューで品質基準をすり合わせ
- 社内スキルに応じて外注比率を調整
最初の3ヶ月は、社内のノウハウが豊富な分野から着手し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。例えば、製造業なら「生産工程の効率化」、IT企業なら「システム導入事例」といったテーマが適しています。
完全内製化を急ぐよりも、半年程度の移行期間を設けることで、社内チームのスキル向上と品質維持を両立できます。各フェーズ終了時にはKPI達成度を測定し、必要に応じて計画を見直す柔軟性も必要です。
理想的なチーム構成と役割分担
編集長、ライター、SEO担当など、各役割の専門性を活かした体制を構築しましょう。組織規模や目的に応じて、ディレクターやプロジェクトリーダー、専門分野の担当者を加えることも有効です。
基本的なチーム構成における各メンバーの主な責任範囲は以下の通りです。
| 役割 | 主な責任範囲 |
|---|---|
| 編集長 | コンテンツ企画・品質管理・進捗管理 |
| ライター | 読者目線の分かりやすい執筆 |
| SEO担当 | キーワード選定・メタデータ最適化 |
編集長はコンテンツ戦略の策定と進行管理、ライターは分かりやすい文章作成、SEO担当は検索順位向上のための技術的対策をそれぞれ担当します。
コアメンバーは専任化しつつ、法律や製品知識が必要な分野では社内の専門家を適宜巻き込む柔軟性が重要です。
承認フローでは3段階チェック体制(執筆→技術校正→最終確認)を導入し、責任範囲を明確にすることが品質維持のポイントです。専門性の高いコンテンツでは、関連部署との連携フローを事前に設計しておきましょう。
品質を担保する制作マニュアルとチェックリスト
品質担保には、制作マニュアルとチェックリストの整備が重要です。記事の目的、ターゲット層、トーン&スタイルを明確に定義した制作マニュアルを作成しましょう。
チェックリストで網羅すべき5つの要素は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本構成 | リード文・見出し階層・文字数配分 |
| SEO要件 | キーワード配置・メタディスクリプション |
| 事実確認 | 統計データの出典明記・最新情報の更新日 |
| 表現規約 | 禁止用語・推奨言い回し |
| 視覚要素 | 画像配置ルール・表の書式 |
例えば、「20代ビジネスパーソン向け実践スキル記事」といったターゲット設定や、「専門用語は脚注で解説」といった表記ルールを統一します。
運用後の改善サイクルも重要です。リードタイム短縮や誤字率低下などの定量データに加え、チームメンバーからの定性フィードバックを定期的に反映させる仕組みが効果的です。
| 改善ポイント | 具体的手法 |
|---|---|
| マニュアル | 月次レビュー+チーム投票による改訂 |
| チェックリスト | 誤字率・リンク切れ数値管理 |
特にSEO要件や表現規約は、検索アルゴリズムの更新に合わせた柔軟な見直しが欠かせません。
定期的な改善により品質を維持しながら制作効率を向上させ、内製化の真の価値を実現できるでしょう。
外注と併用するハイブリッドモデルの実例
ハイブリッドモデルでは、業務特性に応じた最適な役割分担が成功の鍵です。成果を上げている企業の事例から、3つの代表的なパターンをご紹介します。
- 専門性の高い技術記事は外部ライターに依頼し、自社スタッフがキーワード選定と構成案を作成(製造業A社)
- 繁忙期のコンテンツ増強時のみ外注を活用し、平常時は内製チームで対応(B2C企業)
- 社内編集者が外部ライターの原稿をブランド基準に合わせて監修(メディア運営)
特に注目すべきは、あるIT企業が採用した「コアコンテンツ内製化+周辺記事外注化」モデルです。
| タスク種別 | 担当内容 |
|---|---|
| 内製タスク | キーワード調査/構成案作成/最終校正 |
| 外注タスク | 下書き作成/専門分野の深堀り |
重要なのは、外注ライターと継続的に情報共有し、社内ノウハウを伝達することです。月次のコンテンツ戦略会議に外注先を参加させることで、ブランドの方向性とのズレを防いでいる事例もあります。
まとめ
本記事では、記事制作の内製化について解説しました。最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 記事制作の内製化と外注にはそれぞれメリット・デメリットがある
- 業種・目的、社内リソースによって最適な記事制作方法は異なる
- 内製化のメリットは独自の専門知識活用、社内ノウハウ蓄積、意思決定の迅速化
- 内製化の課題は人的コスト、時間的制約、専門スキル不足
- 内製化成功のためには明確な目的設定、チーム構成、制作マニュアルの整備が必要
記事制作の内製化は、コストを抑えつつ品質とスピードを両立させ、効果的なコンテンツマーケティングを実現するものです。
ぜひ、自社に合った方法で記事制作の内製化を進めてみてください。
magicssでは、「SEOコンテンツ制作をしたいけど、社内にリソースがない」という方のために、記事制作代行や内製化支援も行っています。
記事の内製化にお悩みの方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。