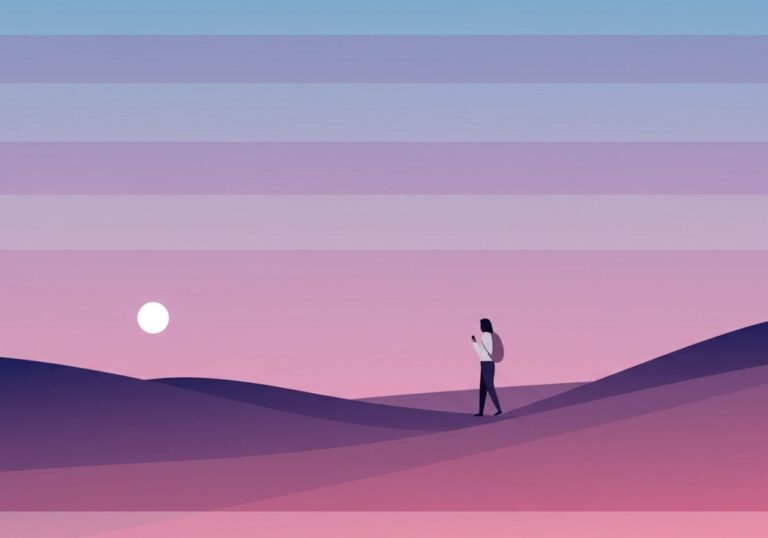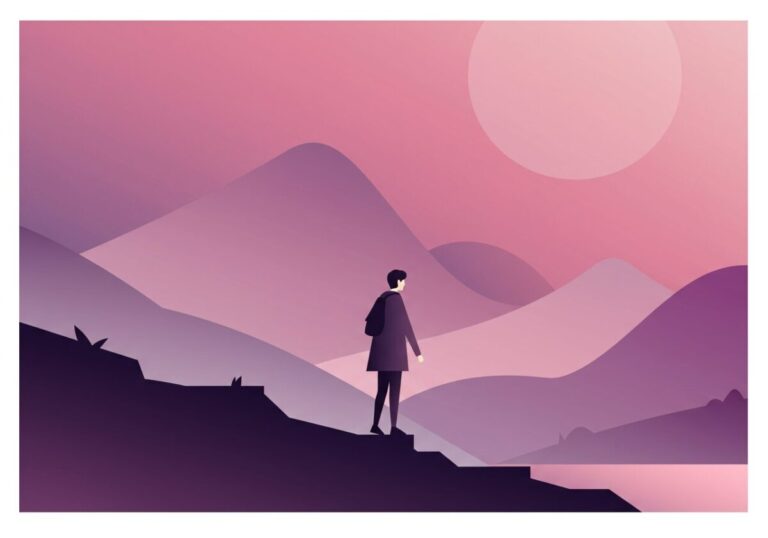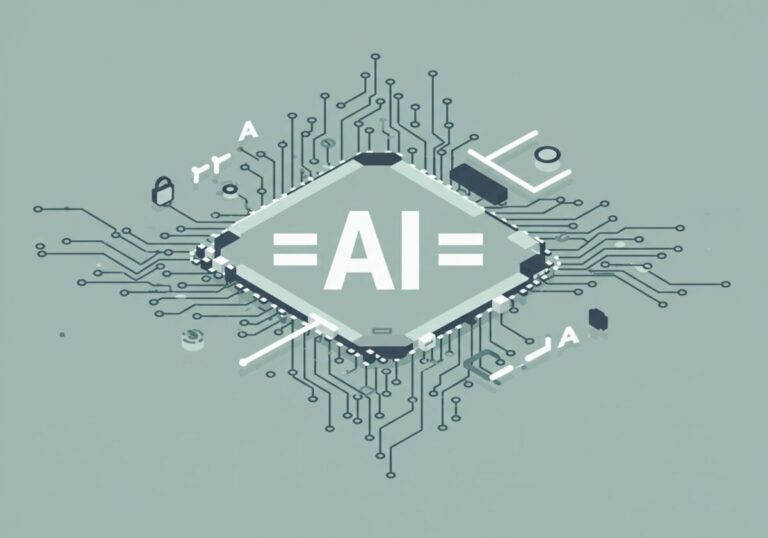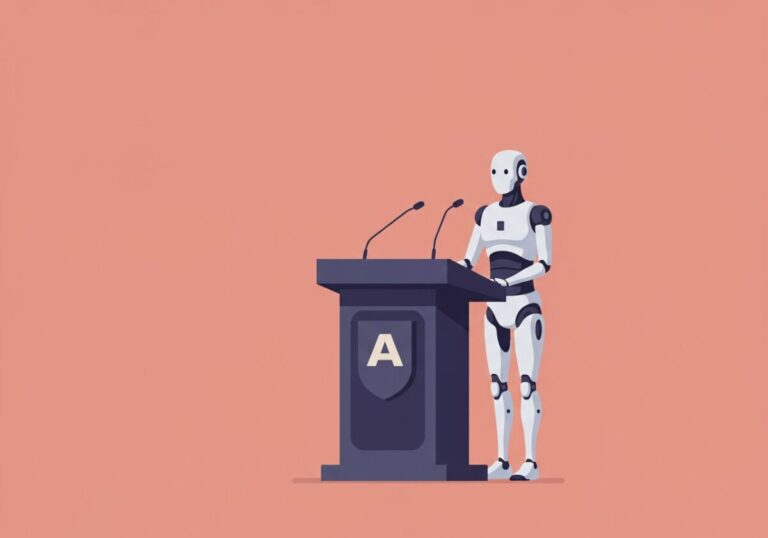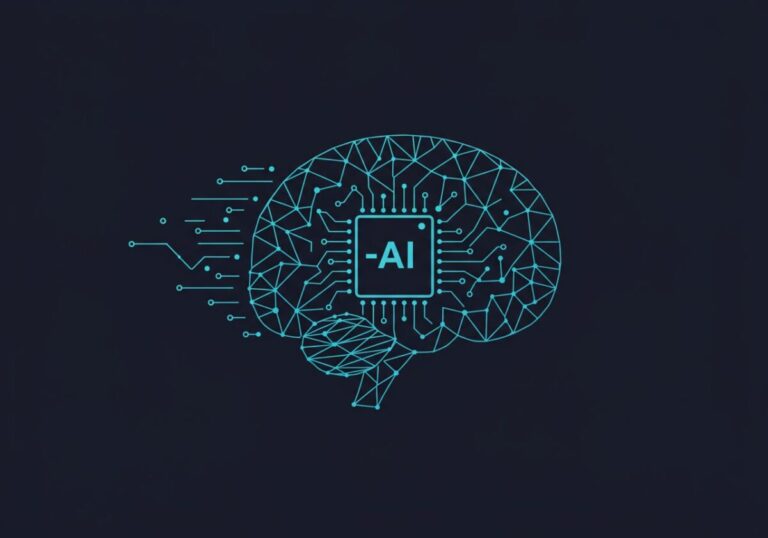- 高校生の生成AI活用で「総合的な探究の時間」が第1位
- 全国330万人の高校生が年間70時間の探究学習に従事
- 大学入試でも生成AI活用型選抜方式が2027年度から導入予定
探究学習での生成AI活用が最多、スタディサプリ調査で判明
スタディサプリが実施した高校生の生成AI使用状況調査において、「総合的な探究の時間などの調べ学習」が活用シーンの第1位となったことが明らかになりました[1]。この調査結果は、教育現場における生成AI活用の実態を示す重要なデータとして注目されています。現役高校生を対象としたこのアンケート調査は、2025年9月に発表され、生成AI利用の具体的な傾向を浮き彫りにしました[2]。
探究学習における生成AI活用の背景には、生徒が直面する具体的な課題があります。別の調査では、高校生の37.4%が探究学習で最も困難な点として「テーマを決めること」を挙げており[3]、このような課題解決の手段として生成AIが活用されている実情が浮かび上がります。調査では生成AIによる誤情報の問題も同時に指摘されているものの、教育現場での活用は着実に進展していることが確認されています。
この調査結果は、教育現場におけるAI活用の新たな段階を示しています。従来の「調べ学習」は図書館やインターネット検索が主流でしたが、生成AIの登場により、まるで知識豊富な個人教師と対話するように情報収集や思考整理ができるようになりました。特に探究学習では、生徒が自ら問いを立て、仮説を検証する過程で、生成AIが「思考のパートナー」として機能していると考えられます。ただし、情報の真偽を見極める批判的思考力の育成が、これまで以上に重要になってきているのも事実です。
探究学習市場の急成長が生成AI活用を後押し
全国の高校生約330万人が年間70時間の探究学習に取り組んでおり、延べ2億3,100万時間という膨大な学習時間が存在しています[4]。現在の探究学習市場規模は約500億円で、年間成長率15-20%を記録し、2030年には1,500億円規模への成長が予測されています。この急速な市場拡大の背景には、教材・コンテンツ不足、専門知識・外部講師不足、評価・管理システムの欠如という3つの深刻な課題があります。
こうした課題を解決する手段として、生成AIへの期待が高まっています。従来は限られた教材や専門知識に依存していた探究学習において、生成AIは豊富な知識ベースと対話的な学習支援を提供する革新的なツールとして位置づけられています。教育現場では、中村学園大学教育学部の山本朋弘研究室が「校務改善の生成型AI活用ガイド」を公開するなど[5]、生成AI活用を支援する取り組みも活発化しています。
探究学習市場の急成長は、まさに教育のデジタル変革の象徴といえるでしょう。年間2億時間を超える学習時間は、東京ドーム約46万個分の時間に相当する膨大な規模です。この巨大な学習時間において、生成AIは従来の「一方向的な情報提供」から「双方向的な学習支援」への転換を可能にしています。例えば、生徒が「環境問題について調べたい」と思った時、生成AIは単に情報を提供するだけでなく、「どの角度から調べたいか」「地域の課題と関連付けたいか」といった質問を通じて、生徒の思考を深める役割を果たしています。
大学入試制度にも変化、生成AI活用型選抜が登場
教育現場での生成AI活用の広がりは、大学入試制度にも大きな変化をもたらしています。iU情報経営イノベーション専門職大学は、2027年度入試の総合型選抜において「生成AI活用型」選抜方式を新設することを発表しました[6]。同大学はAIを「共創のパートナー」と捉え、全学的なAI方針を導入しており、この取り組みは日本初の試みとして注目されています。
新しい選抜方式では、「生成AIを活用した成果物の提出」「プロンプトエンジニアリングの質や工夫」「成果物に対する改善・修正能力」などが評価項目に含まれます。これは従来の知識量競争から、AIとの協働による創造的問題解決力を評価する新しい入試形態を示しており、高校生の生成AI活用スキルが直接的に評価される時代の到来を予感させます。
この入試制度の変化は、教育界における「パラダイムシフト」の象徴です。従来の入試は「記憶した知識をいかに正確に再現するか」が重視されていましたが、生成AI時代では「AIとどのように協働して新しい価値を創造するか」が問われるようになります。これは、まるで楽器の演奏からオーケストラの指揮へと求められるスキルが変化するようなものです。プロンプトエンジニアリングは、AIという「優秀な楽器」から最高の演奏を引き出す「指揮者」のスキルといえるでしょう。高校生たちは今、この新しい時代に必要な「AI協働スキル」を自然に身につけているのです。
まとめ
高校生の生成AI利用実態調査により、探究学習での活用が最多となっていることが明らかになりました。全国330万人の高校生が取り組む探究学習において、生成AIは重要な学習支援ツールとして定着しつつあります。市場規模の急成長と教育現場の課題解決ニーズが相まって、生成AI活用はさらに加速すると予想されます。大学入試制度の変化も含め、教育現場全体でAI協働時代への適応が進んでいることが確認できました。
参考文献
- [1] 活用シーン1位は「総合的な探究の時間などの調べ学習」 高校生の生成AI使用状況を調査 スタディサプリ
- [2] 現役高校生が回答「生成AIに関するアンケート」=スタディサプリ進路調べ=
- [3] 探究学習で難しかったこと、高校生の37.4%が「テーマを決めること」と回答
- [4] 探究学習市場で新規事業を創出する方法
- [5] 管理職向けの「校務改善の生成型AI活用ガイド」を公開
- [6] iU 情報経営イノベーション専門職大学 2027年度入試に「生成AI活用型」選抜方式を新設
*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。