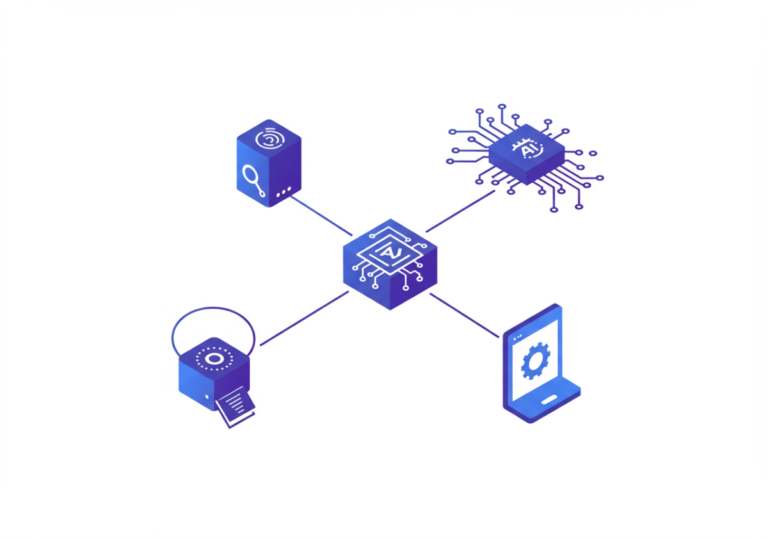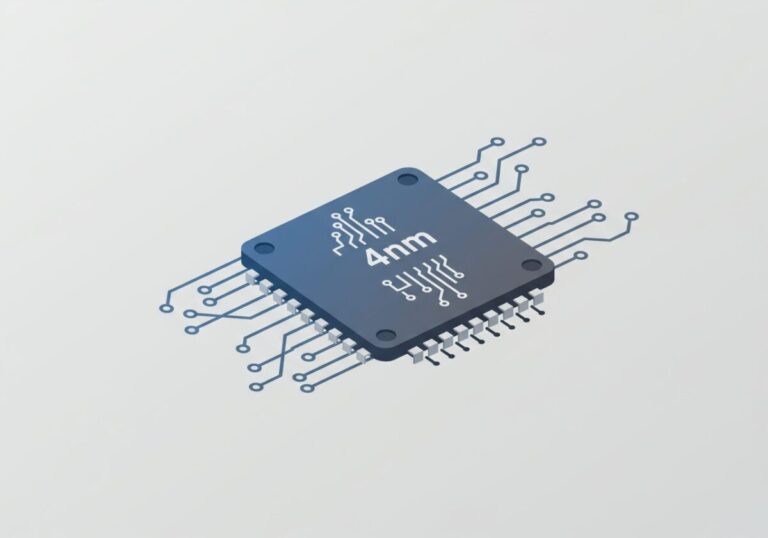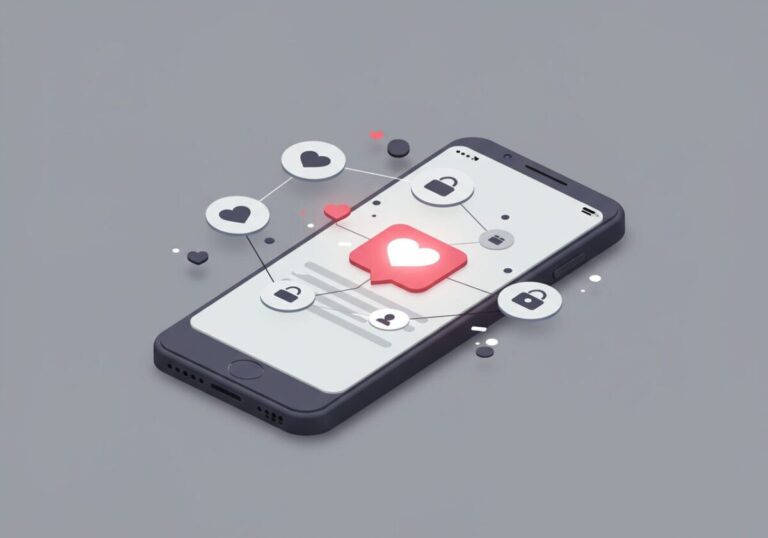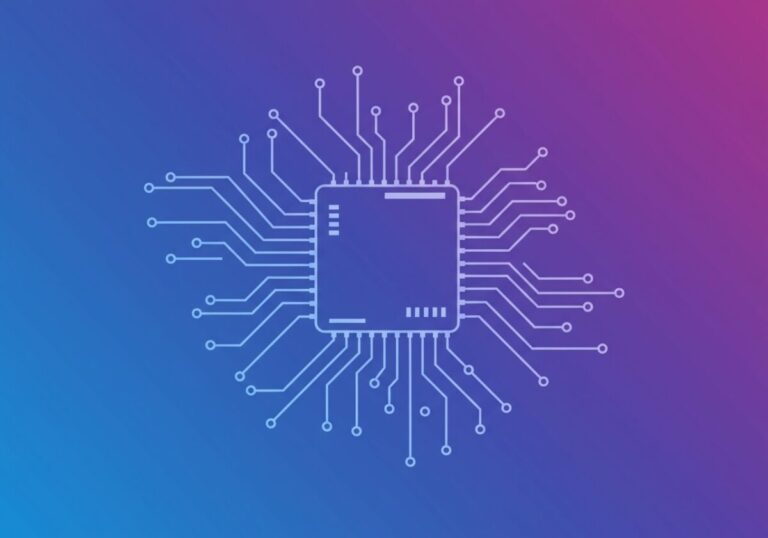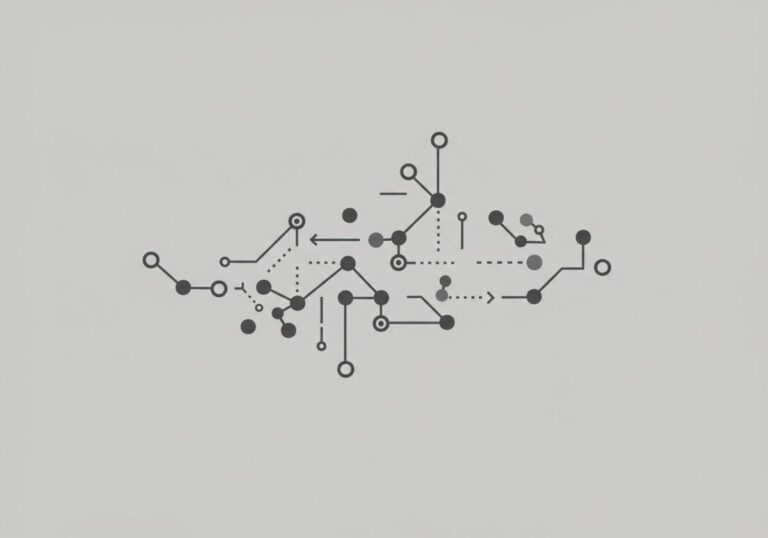- LinkedInが2025年11月3日からユーザーデータでAI学習を開始
- デフォルトでオプトイン設定のため手動でのオプトアウトが必要
- プライバシー設定から「生成AI改善のためのデータ」で無効化可能
LinkedInのAI学習計画の全貌
Microsoft傘下のLinkedInは、2025年11月3日からメンバーのプロフィール、投稿、履歴書、公開活動データを生成AI モデルの学習に使用することを発表しました[1]。この取り組みは、EU、EEA、スイス、カナダ、香港のユーザーを対象とし、「正当な利益」という法的枠組みの下で実施されます[2]。18歳未満のユーザーのデータは除外されますが、成人ユーザーは自動的にオプトインされる仕組みとなっています。
この決定は、OpenAIなどの競合他社が求人プラットフォーム分野に参入する中で、LinkedInが競争力を維持するための戦略的な動きと位置づけられています[2]。同時に、Microsoftの広範なAI戦略の一環として、より多くのデータをAIエコシステムに供給する取り組みでもあります[3]。
この発表は、プラットフォーム企業がユーザーデータをAI学習に活用する新たな潮流を象徴しています。LinkedInのような職業特化型SNSのデータは、履歴書や職歴情報など高品質な構造化データが豊富で、AI学習には非常に価値が高いのです。しかし、ユーザーの明示的な同意なしにデフォルトでオプトインする手法は、プライバシー保護の観点から議論を呼んでいます。これは、革新的技術の発展とユーザーのプライバシー権のバランスをどう取るかという、現代のデジタル社会が直面する根本的な課題を浮き彫りにしています。
オプトアウト手順とプライバシー設定の重要性
ユーザーがAI学習からデータを除外するには、LinkedInの「データ・プライバシー」設定から「生成AI改善のためのデータ」オプションを無効にする必要があります[1]。ただし、重要な点として、オプトアウト後に収集されるデータのみが保護され、それ以前のデータは学習環境に残り続けることが明記されています[1]。
この仕組みは、カリフォルニア州でLinkedInがプライベートメッセージを秘密裏にAI学習に使用していたとして訴訟を起こされた背景もあり、透明性の向上を図る取り組みとも解釈できます[3]。しかし、プライバシー擁護団体からは、デフォルトでオプトインする設定に対する懸念の声が上がっています[2]。
オプトアウトの仕組みを理解することは、現代のデジタルリテラシーの重要な要素です。多くのユーザーは設定変更を行わないため、デフォルト設定の影響は極めて大きくなります。これは「ナッジ理論」として知られる行動経済学の概念で、選択肢の提示方法が人々の行動に大きく影響することを示しています。LinkedInのケースでは、企業側に有利なデフォルト設定により、大多数のユーザーデータがAI学習に使用される可能性が高いのです。ユーザー自身が積極的にプライバシー設定を確認し、自分の意思に沿った選択をすることが、これまで以上に重要になっています。
GDPR時代のデータ利用と「正当な利益」の解釈
LinkedInは今回の取り組みを「正当な利益」という法的根拠に基づいて実施しています[2]。これは、より厳格な同意要件を回避する抜け穴として機能する可能性があり、GDPR(一般データ保護規則)などのデータ保護規制との緊張関係を浮き彫りにしています[2]。
この動きは、技術革新とデータ保護規制の間で生じる複雑な法的課題を示しており、6つの国際的なニュースソースで報道されるなど、世界的な関心を集めています[4]。AI企業のデータに対する需要が高まる中で、プラットフォーム企業がユーザー生成コンテンツを活用する傾向は今後も続くと予想されます[5]。
「正当な利益」という概念は、GDPRの中でも最も解釈が分かれる部分の一つです。これは、企業の事業上の利益とユーザーのプライバシー権を天秤にかけ、前者が後者を上回る場合に適用される原則です。しかし、この判断基準は主観的で、企業側に有利に解釈される傾向があります。LinkedInのケースは、この法的グレーゾーンを活用した事例として、今後の判例や規制の方向性を決める重要な試金石となるでしょう。ユーザーとしては、法的な保護に頼るだけでなく、自らの権利を理解し、積極的に行使することが求められています。
参考文献
- [1] LinkedIn set to start to train its AI on member profiles
- [2] LinkedIn to Train AI on User Profiles and Posts from November 2025
- [3] LinkedIn will use your data for AI. Here’s how to opt out
- [4] LinkedIn Set to Start to Train Its AI on Member Profiles
- [5] LinkedIn to Share User Data with Microsoft for AI
*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。