AI技術の進化により、企業の業務効率化が加速しています。
AI関連の多種多様なサービスおよびツールが登場しており、大企業だけでなく中小企業もAIを導入しやすい環境だと言えるでしょう。
しかし、以下のような悩みでAI導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
- AIを活用する具体的な方法が分からない
- AIで業務効率化するメリットを知りたい
- AIを導入する際に注意すべき点が気になる
結論から言うと、AI導入は問い合わせ対応から品質チェックまで幅広い業務を自動化でき、労働力不足の解消や品質の向上といったメリットをもたらします。
本記事では、AIを活用した具体的な導入事例やメリット、注意点などを詳しく解説します。
自社でAIを導入して業務改善を効率的に実現するヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
AI活用による業務効率化の事例6選

AIによる業務効率化の具体例を6つ紹介します。
- 問い合わせに自動対応するチャットボット
- 画像や文章などのコンテンツ作成
- 議事録の自動生成
- 契約書や帳票の自動処理
- 営業トークや顧客データの分析自動化
- 製造物の品質チェック・異常検知
1.問い合わせに自動対応するチャットボット
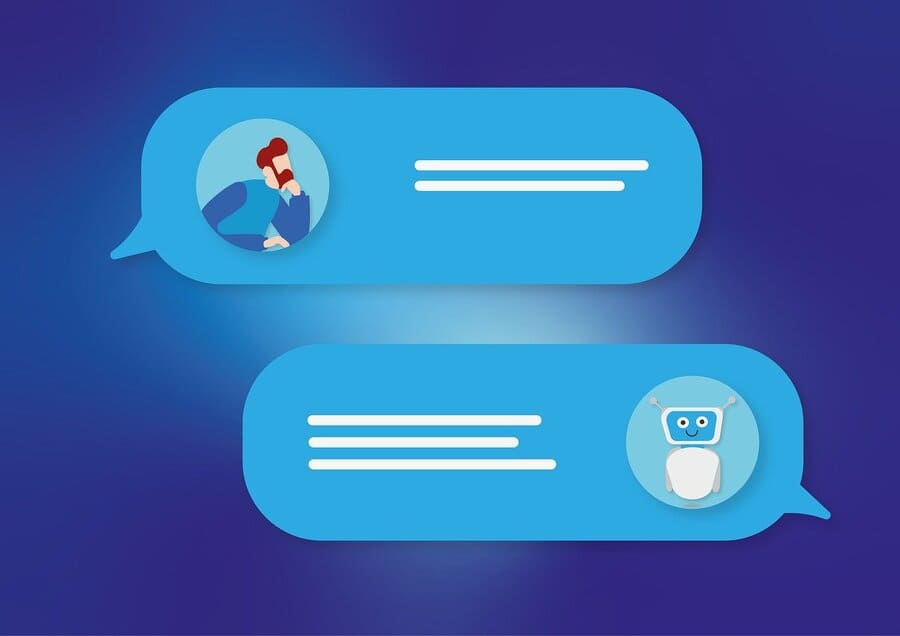
AIを利用したチャットボットに顧客応対を任せることで、問い合わせ対応の効率や品質の向上が期待できます。
チャットボットとは、AIの自然言語処理技術を活用して顧客の問い合わせ内容を判断し、事前に用意した回答データベースから最適な返答を探して表示する自動対応システムです。
導入してから三カ月で、対応時間を6割削減したうえで正答率95%以上を実現した例も。
高度な判断が必要な案件に人間のオペレーターが対応するといった役割分担によって、業務効率と顧客満足度の両立を目指せるでしょう。
チャットボットを提供しているサービスの例は以下のとおり。
2.画像や文章などのコンテンツ作成

画像や文章などのコンテンツ作成においては、生成AIが活用されています。
コンテンツ生成AIツールに短いテキスト文を入力するだけで、クオリティの高いコンテンツが1分とかけずに生成可能です。
生成したコンテンツを叩き台にして、手作業で微調整を加えることで、コンテンツの制作時間を大幅に短縮できます。
ほかにも、以下のような場面で活用可能です。
- コンテンツや企画のアイデア出し
- 既成コンテンツのパターン変更(色を変える、作風を変える等)
- 文章の添削・推敲
- 動画の自動カット編集や字幕生成
代表的なAI生成ツールは以下のとおり。
| サービス・ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Stable Diffusion | ローカル環境で動作可能な画像生成ツール |
| Midjourney | Discord上で動作する画像生成ツール |
| Canva | シームレスに編集できる画像生成ツール |
| Notion AI | 幅広い用途で使える文章生成ツール |
| Catchy | 国内最大級の文章生成ツール |
| Claude | 自然な文章を出力しやすい文章生成ツール |
3.議事録の自動生成

多くの企業が実施している議事録の作成業務は、AIを活用した自動生成システムを利用することで労力と時間を節約できます。
会議する際に自動生成システムを活用してできることは以下のとおり。
- 音声のリアルタイムな文章化
- 議題や決定事項の抽出
- 発言者の判別と名前付与
- 多言語での翻訳
- バックアップ保存と共有
人間が作成する場合、聞き逃した内容を会議中に聞き返したり、録音を何度も聞き直したりするといった労力と時間がかかります。
しかし、AIによる自動生成システムであれば、会議が終了するときには自動的に議事録が完成するため、コストを大きく削減できます。
議事録を自動生成できるサービスの例は以下のとおり。
| サービス・ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| ユーザーローカル 音声議事録システム | 無料で利用できる |
| Notta | 多機能でコスパが良い |
| AI議事録取れる君 | 自動要約や共同編集など機能が豊富 |
無料トライアルが利用できるツールが多いため、自身の業務にあったツールを選ぶと良いでしょう。
4.契約書や帳票の自動処理

契約書や帳票のように、処理する内容が決まっている書類は、AIに任せるのが効率的です。
AIを利用した画像認識機能とOCR(光学文字認識)技術を活用したAI-OCR技術によって、書類に書かれた情報を高精度かつ瞬時に抽出できます。
たとえば、契約書であれば契約者の名前や契約期間、金額などの主要項目を抽出し、データベースに登録することまで可能です。
AI-OCRを導入したことで、作業時間を約57%削減した事例もあるので、生産性の向上が見込めるでしょう。
人件費削減にも繋がるため、大幅なコストダウンが期待できます。
帳票の自動処理に対応しているAIサービスの例は以下のとおり。
| サービス・ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| LawFlow | 2022年12月より無償化した契約書チェックツール |
| LFチェッカー | 導入者数No.1のLegalForceが提供する契約書チェックツール |
| WisOCR | 累計出荷数1000万を突破したPanasonic製の帳票読み取りサービス |
| Paperoid | 文字認識率99.22%のAI-OCRエンジンを用いた帳票読み取りサービス |
| 日立製作所 帳票認識サービス | 確信度スコアによる仕分けが可能な帳票読み取りサービス |
5.営業トークや顧客データの分析自動化

人と人が対話する営業の分野でも、AIを活用して営業トークや顧客データを分析して業績改善に繋げられます。
たとえば、成果を上げた際の営業トークを集め、共通するキーワードや状況を探すことで、売上に繋がる成功パターンを抽出できます。
顧客の取引データや行動履歴も併せて分類・整理すれば、顧客ごとに適切なアプローチ方法を導き出せるでしょう。
営業の活動量や効率が向上するのはもちろん、新人を教育する手間が軽減できる点も注目です。
AIを活用する営業向けサービスの例は以下のとおり。
| サービス・ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| HubSpot | 複数のAIサービスが集約されたカスタマープラットフォーム |
| Magic Moment Playbook | 活動改善やアプローチを自動化できるAI営業プラットフォーム |
| Salesforce | クラウド型のオールインワンCRMツール |
6.製造物の品質チェック・異常検知

製造業におけるAI活用の代表例として、品質チェックや異常検知の自動化が挙げられます。
画像認識AIを用いた検品システムは、製造ラインに設置したカメラで撮影した製品画像を瞬時に分析し、微細な傷や変形を高精度で検出。
人間の目では見逃しやすい些細な不具合も漏れなくチェックできるため、品質チェックの品質向上と効率化を同時に実現できます。
毎日10万個の目視検査をしていた企業が導入した結果、検査数を95%削減することに成功しました。
人件費削減にも繋がるため、大幅なコストダウンが期待できるでしょう。
製造物の品質をチェックできるAI外観検査システムの例は以下のとおり。
| サービス・ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Phoenix Vision | 無料の検証テストを実施している |
| AISIA-AD | 顧客に合った条件でシステムを構築する |
| InspectAI | 良品画像のみで高精度な検査ができる |
仕事にAIを導入する5つのメリット

AIの導入は、以下のようなメリットを企業にもたらし、競争力を高める一助となります。
- 労働力不足を解消できる
- 顧客満足度を高められる
- 学習によって精度が向上する
- 人為的ミスや属人化を防げる
- 働き方改革やDXの推進に繋がる
それぞれのメリットについて詳しい解説を見ていきましょう。
1.労働力不足を解消できる
AI導入のメリットとして挙げられることが多いのが、労働力不足の解消です。
単純作業を自動化することで、少ない労働力でも業務を回せるようになります。
また、翻訳のように専門性の高いスキルが必要な業務でも、対応できるAIを導入すればOKです。
24時間365日稼働できる点も、労働力の軽減に役立つAIの強みと言えるでしょう。
2.顧客満足度を高められる
AIを活用するとサービスの品質向上や時間短縮ができるため、顧客満足度を向上させることにも繋がります。
たとえば、以下のようなデータを収集・分析することで、顧客に合ったサービスや商品を提案できます。
- 顧客の閲覧および購入の履歴
- 問い合わせ内容から読み取れる感情
- カメラで撮影した顧客の表情
上記のような雑務をAIがこなしてくれるため、人間の労働者はより高度な対応や判断に注力できるように。
AIと人間の双方でサービスの品質が高まれば、ますます顧客の満足度は向上していくでしょう。
3.学習によって精度が向上する
継続的な学習によって精度が向上する点も、AIを利用するメリットの一つです。
最初の精度が低くても、使用するなかで学習を積み重なっていくため、徐々に改善していきます。
たとえ導入当初の正答率が半分程度だったとしても、3か月後には8〜9割まで改善することも。
最終的には人間よりも高い精度で良い結果が出せるようにもなります。
AIの試行回数をどんどん増やし、新人を育てるつもりでフィードバックするのがおすすめです。
4.人為的ミスや属人化を防げる
人為的ミスや業務の属人化は、AIを導入すれば効果的に防げます。
人間の判断は気分や経験によってブレが生じやすいため、作業者によって品質がバラついたり、ミスしたりする可能性があり不安定です。
いっぽう、AIは学習した判断基準で一貫しており、より安定した結果を得られます。
ベテラン社員の暗黙知や経験則をAIに学習させれば、新人でも高品質な結果を出せるように。
特定の人間が不調だったりいなくなったりしても問題が出ない安定した品質提供を目指すなら、AIの導入が適しています。
5.働き方改革やDXの推進に繋がる
AIを導入すると、働き方改革やデジタルトランスフォーメーション(DX)に貢献していると認められる可能性が高いです。
デジタル技術を導入してビジネスモデルを変革する取り組み。単純なデジタル化とは異なる。
働き方改革やDXは、日本企業の競争力を高めるために国が推進しています。
そのため、積極的な改革に取り組んでいる企業に対して、以下のような補助金や助成金が用意されています。
- IT導入補助金
- 事業再構築補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
毎年公募しているものもあるので、補助金を狙って計画を立てるのも良いかもしれません。
AIを活用する際の注意点5つ
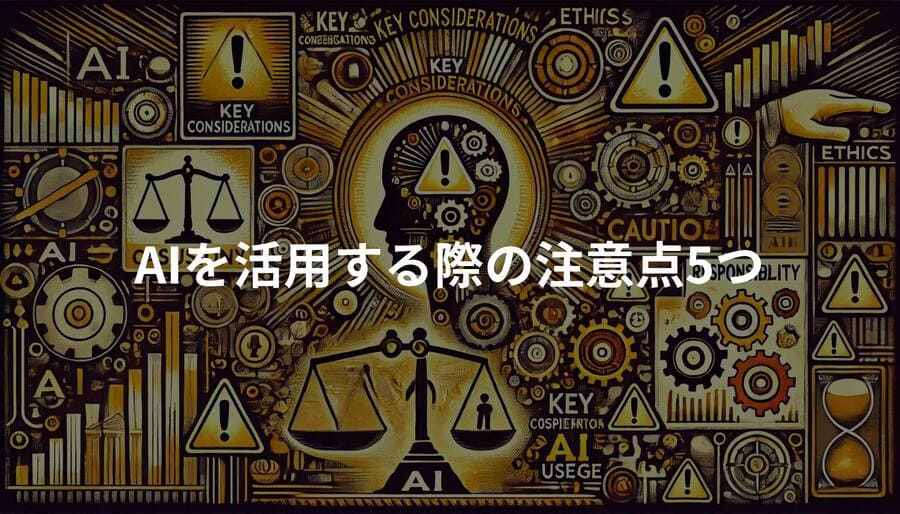
AIの導入にはメリットが多いですが、以下のような注意点もあります。
- 目的を明確にしてから導入する
- 大量の学習データが必要
- AIの知識を持つ人材が必要
- AIに業務を一任しない
- 情報が漏えい・流出しないようリスク管理する
ここでは注意点について詳しく解説するので、AI導入前にチェックしてください。
1.目的を明確にしてから導入する
AIを導入する際、明確な目的を設定することが重要です。
明確に目的がなければ、AIを導入した効果を客観的に見るのが難しくなり、効率よく改善できなくなります。
あらかじめ具体的な数値目標を掲げ、導入後はデータを計測しながらゴールを目指しましょう。
たとえば、以下のような目標が考えられます。
- 顧客への対応時間を30%削減
- 顧客満足度を10%向上
- 不良品率を10%減少
AI導入の効果を評価するタイミングを作るために、目標達成までの期限も決めておくと良いでしょう。
2.大量の学習データが必要
AIモデルの精度を高めるには、質の高い学習データが大量に必要です。
用意するデータが多ければ多いほど、より正しい判定を下しやすくなります。
また、データは対応すべき分野を網羅しており、正確かつ最新でなければなりません。
データが不足していたり間違っていたりすれば、AIを導入しても作業効率が落ちる可能性も。
つねに学習し続けるため、データを保管する場所(ハードディスク等)の容量には十分なスペースが必要な点にも気をつけてください。
3.AIの知識を持つ人材が必要
AIを効率的に活用するには、専門知識を持つ人材が不可欠です。
もし現時点で知識を持つ人材がいなければ、以下のような方法で確保する必要があります。
- AIの知識を持つ人材を新たに採用する
- 教育プログラムを組んで育成する
- AI導入支援サービスにサポートしてもらう
データ分析やプログラミングに興味のある人であれば、AI分野の専門的な知識まで修得できる見込みがあるでしょう。
自社での教育が難しければ、新規雇用や支援サービスの利用を検討してみてください。
4.AIに業務を一任しない
AIによって業務効率が向上できても、すべての業務をAIに任せきりにするのは危険です。
AIは学習した内容を丸写ししたり、間違った内容を出力したりする可能性があるため、知識や経験を持つ人間によるチェックが必要になります。
もしチェックを怠れば、著作権を侵害するコンテンツや、事実とは異なる数値データが生成されても気付けません。
AIの判断を無条件に信頼せず、人間による最終確認と承認プロセスを設けることが重要です。
あくまでAIは補助ツールとして活用し、最終的には人間が意思決定するようにしましょう。
5.情報が漏えい・流出しないようリスク管理する
AIを活用する際、機密情報や個人情報が流出しないよう対策をとらなければなりません。
もしセキュリティ性の低いAIシステムを利用してしまうと、学習データに利用した機密情報が外部に漏れる可能性があります。
データの暗号化や匿名化を徹底し、万が一情報が流出しても被害が最小限に抑えられるよう備えてください。
人的要因で機密が漏れないように、情報の取り扱いに関する社内ガイドラインを策定することも重要です。
AIを利用する業務やデータの範囲を明確化し、個人個人のセキュリティ意識まで気を配りましょう。
AIの業務効率化に関するQ&A
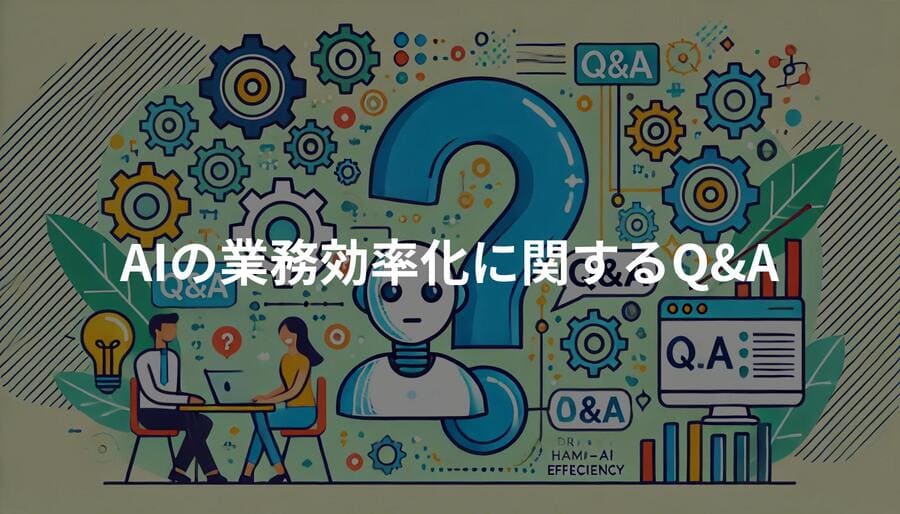
AIの業務効率化に関する、よくある質問と回答を紹介します。
- AI導入に適している業種は何ですか?
- 他にどんなAIツールが業務効率化に使えますか?
- 自社での具体的な活用方法がイメージできません
- RPAとの違いは何ですか?
AI導入に適している業種は何ですか?
AIは学習させる必要性があるので、とくに大量のデータを扱う業種で活用できます。
以下はAI導入が適している業種の一例です。
- 小売業
- 製造業
- 金融業
- 営業
ただし、どんな業界でもAIを導入する余地はあるでしょう。
たとえば、AIが向いていないと言われるクリエイティブな仕事(アーティストなど)でも、アイデア出しや試作などの用途でAIが活用されています。
経済産業省のサイトに掲載されているAI導入ガイドブックなども参考にしてみてください。
他にどんなAIツールが業務効率化に使えますか?
汎用的に導入しやすいAIツールとしては、ChatGPTやCopilot、Geminiのような対話型AIサービスが挙げられます。
対話型AIサービスは、人と話すように指示することで提案や添削、生成などの返答を出力します。
以下のような指示をすれば、業務効率化に役立つでしょう。
- 〇〇のアイデアを出してほしい
- 〇〇の画像を生成してほしい
- 〇〇の文章を翻訳したうえで要約してほしい
- 〇〇のデータをCSV形式に変換してほしい
無料でも利用できるので、AIを導入する前に一度触れてみてください。
自社での具体的な活用方法がイメージできません
どうしても導入するイメージができない場合は、AI導入コンサルタントに相談するのも1つの手です。
AI導入コンサルタントはAIに関する専門的な知識を有しており、導入から戦略立案、データ収集、アルゴリズム構築までサポートしてくれます。
自力で導入するよりも短期間でAIを構築できるので、気になったら利用を検討してみてください。
以下は、AI導入コンサルタントの一例です。
RPAとの違いは何ですか?
RPAは同じ作業を繰り返す自動化ツールであるのに対し、AIは複雑な判断や予測もできます。
操作する内容に変化のない単純作業にはRPAが向いており、効果がすぐに出やすいです。
AIは学習時間が必要なものの、幅広い分野に対応できるため長期的な価値を生み出せるでしょう。
AIが分析するデータをRPAで収集するといった形で、両者の特徴を活かして組み合わせれば、より高度な業務効率化が実現できます。
まとめ
本記事では、AIによる業務効率化について解説しました。
最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。
- AIを活用したチャットボットやコンテンツ生成などで業務を効率化できる
- AIの導入には労働力不足の解消や顧客満足度の向上といったメリットがある
- 導入する際は専門知識を持つ人材や大量の学習データが必要
- 計画や運用に不安があればAI導入コンサルタントに相談するのも手
作業時間の短縮やコスト削減、人的ミスの軽減などが実現できるAI導入は、多くの企業で注目を集めています。
本記事を参考にAI導入を検討し、自社の業務改善に活かしていただければ幸いです。

