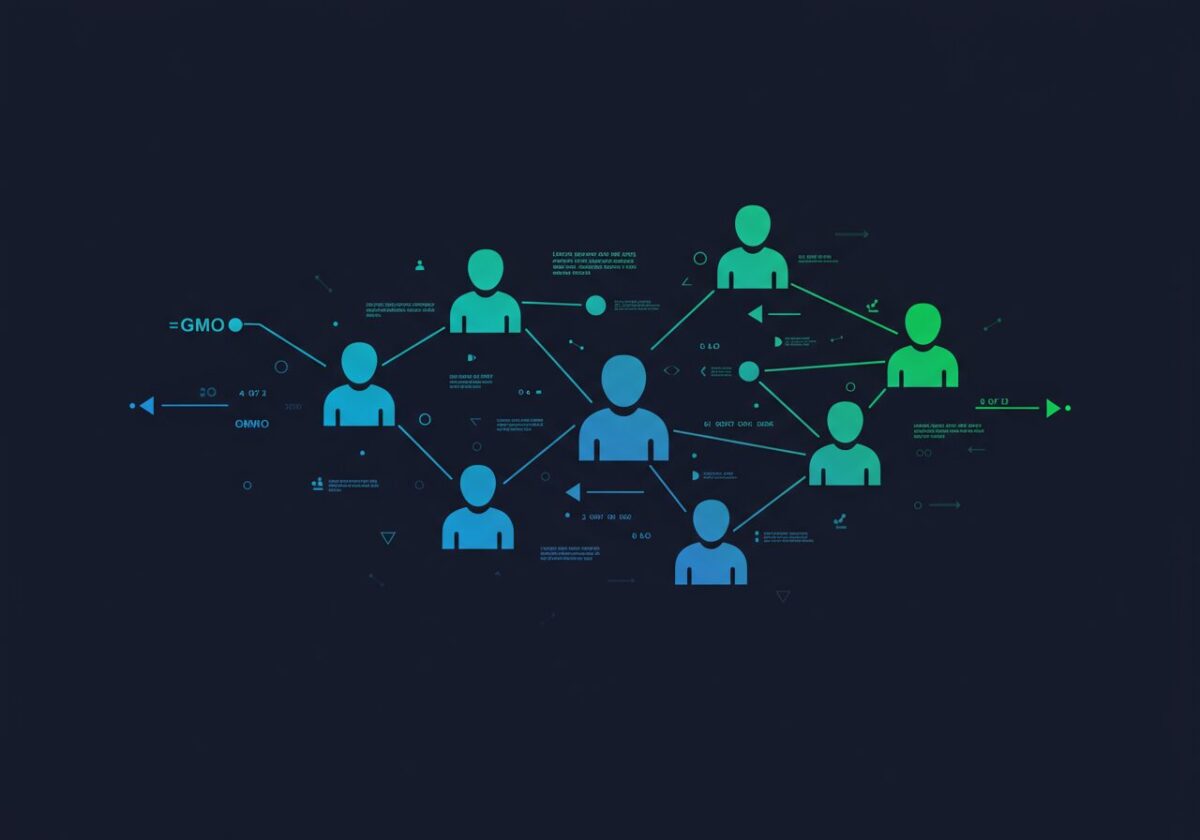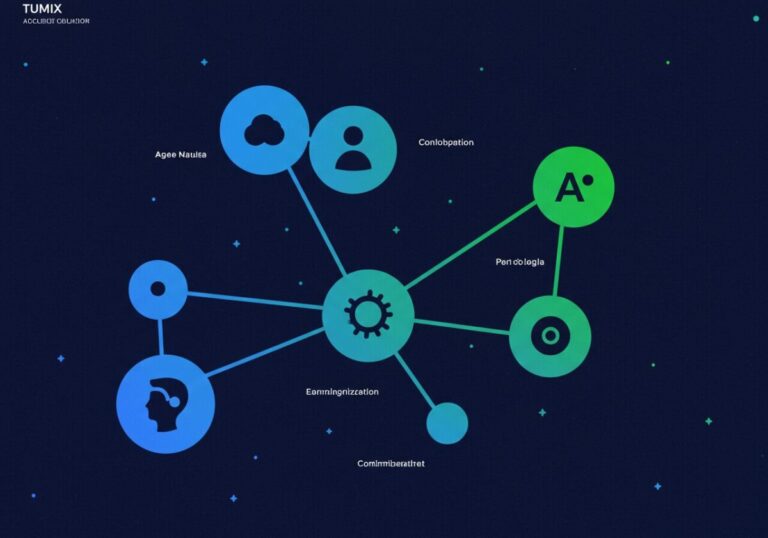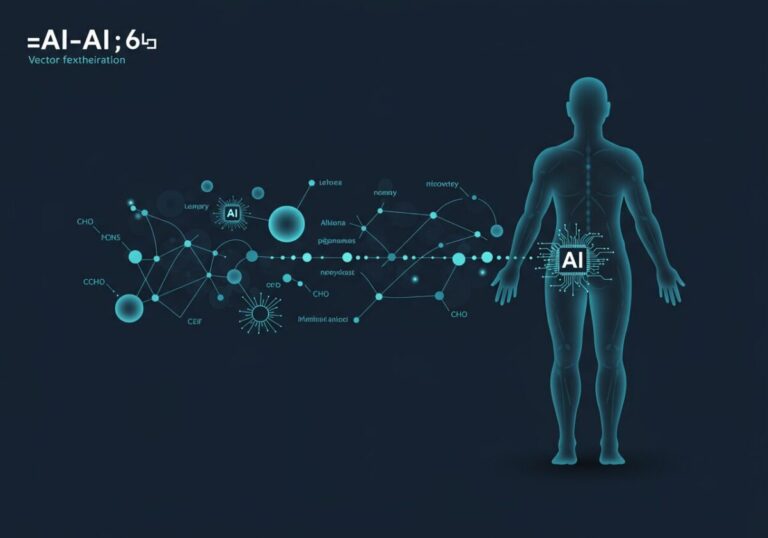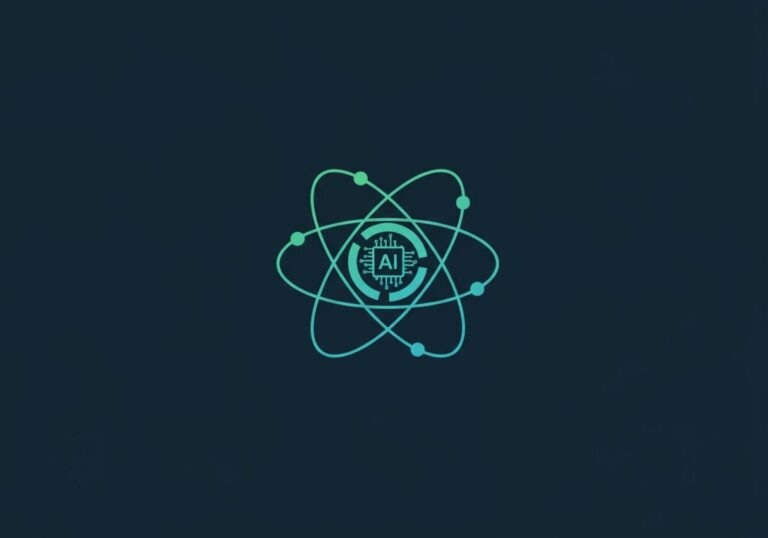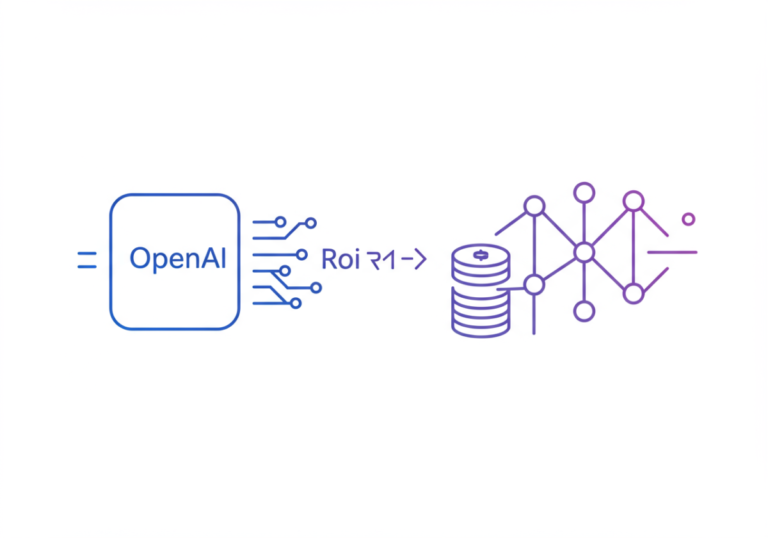- GMOが生成AI活用により月間25.1万時間の業務削減を実現
- 複数AIサービス利用率が80%に達し、1年前から約1.5倍に拡大
- グループ全体の95%が生成AIを導入、日常業務に深く浸透
月間25万時間の業務削減を実現―1572人分の労働力に相当
GMOインターネットグループが2025年9月に実施した四半期生成AI利用実態調査において、驚異的な成果が明らかになりました。同社グループ全体での生成AI導入率は95.0%に達し、月間の業務時間削減効果は約25万1000時間に上ることが判明しました[1]。この削減時間は1572人分の労働力に相当する規模となっています。
特に注目すべきは、AIユーザーの73.6%がほぼ毎日生成AIを活用し、93.1%が週に1回以上利用している点です[1]。これは単なる試験導入を超えて、日常業務の中核に生成AIが組み込まれていることを示しています。前回調査から0.9ポイント上昇した導入率は、組織全体でのAI活用が着実に浸透していることを物語っています。
この数字を身近な例で考えてみると、従来1000人の企業が同じ業務量をこなすのに必要だった人員が、生成AI活用により約640人で済むようになったということです。これは単なる効率化を超えて、企業の競争力そのものを根本的に変える変革と言えるでしょう。特に人材不足が深刻化する日本企業にとって、この労働力創出効果は極めて重要な意味を持ちます。ただし、削減された時間をより創造的で戦略的な業務にどう振り向けるかが、真の価値創出の鍵となります。
複数AIサービス利用が1.5倍に急拡大―戦略的AI活用の進化
調査結果で最も印象的なのは、複数のAIサービスを活用する利用率が80.0%に達し、1年前の調査から約1.5倍に増加した点です[1]。これは単一のAIツールに依存するのではなく、用途や目的に応じて最適なAIサービスを使い分ける、より成熟したAI活用段階に移行していることを示しています。
この傾向は、GMOグループが「AIで未来を創るNo.1企業グループ」を目指すという戦略的ポジショニングと密接に関連しています[1]。複数AIサービスの併用により、文書作成、データ分析、コード生成、画像処理など、多様な業務領域で最適化された効率向上が実現されていると考えられます。
複数AIサービスの利用拡大は、まさに「AIツールボックス」の概念を体現しています。大工が作業内容に応じてハンマー、のこぎり、ドライバーを使い分けるように、現代のビジネスパーソンは文章生成AI、画像生成AI、データ分析AIを適材適所で活用する時代に入ったのです。この1.5倍という成長率は、AI活用の初期段階から実用段階への移行を示す重要な指標です。企業がAIを「試してみる」段階から「戦略的に使いこなす」段階へと進化していることを物語っています。
日本企業のAI活用モデルケースとしての意義
GMOグループの成果は、日本企業におけるAI活用の先進事例として重要な示唆を提供しています。95%という高い導入率と、実際の業務時間削減という定量的成果の組み合わせは、AI導入の成功パターンを明確に示しています。特に、段階的な導入拡大により組織全体でのAI活用文化を醸成した点は、他企業にとって参考になるアプローチです。
また、四半期ごとの継続的な調査実施により、AI活用の進捗を定量的に把握し、改善につなげている点も注目に値します。これは単なる技術導入ではなく、組織変革としてAI活用を捉えている証拠と言えるでしょう[1]。
GMOの事例は、AI導入における「日本型アプローチ」の成功モデルを示しています。欧米企業が大胆な変革を一気に進めるのに対し、日本企業は段階的で着実な導入を好む傾向があります。GMOの95%導入率達成は、この日本的なアプローチでも十分に高い成果を上げられることを証明しました。重要なのは、導入率の高さだけでなく、実際の業務改善につながっているという点です。多くの企業がAI導入で苦戦する中、GMOの成功要因を分析し、自社の状況に合わせて応用することが、日本企業のAI活用推進において極めて重要になるでしょう。
参考文献
*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。